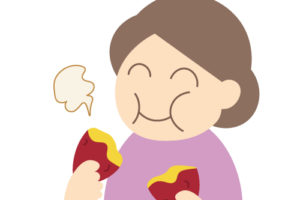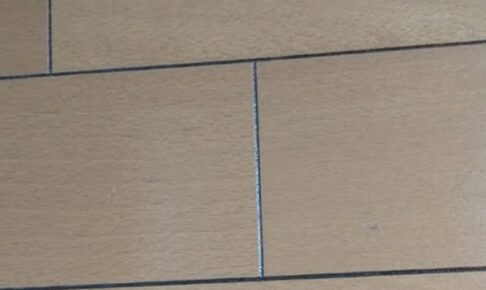日本の朝食によく目にするおかず『焼き鮭』
私は鮭の身はもちろん、皮も好きで残さず食べます。
皮が好きな人の中にはパリパリに焼いた皮が好きっていう人もいますね。
私も食感的にパリパリのほうが好きなんですが、そんなに焼いてしまって栄養素が壊れてないか気になりませんか?
また、『どうしても皮と身の間のぬめりが苦手で食べられない』という人も私の周りで少数いるんですが、すごくもったいないことしてるんですよ。
この記事では、『皮に含まれる栄養成分について』と『皮に含まれる栄養を保持する調理方法』をお話していきます。調理の仕方によっても栄養の含まれる量が変わってきてしまうので、どんな調理方法がベストなのかチェックしてくださいね。
鮭の皮に含まれる栄養成分
鮭の皮には意外と栄養があるんですよ(^^)
- DHA
- EPA
- ビタミンA
- ビタミンB1
- ビタミンB2
- コラーゲン
このように鮭の皮にはオメガ3脂肪酸であるDHA・EPA、カルシウム、ビタミン類やコラーゲンが含まれています。
DHA・EPA
DHA・EPAはオメガ3脂肪酸の一種で、私達の体内では作ることができない成分なので、食べ物から摂る必要がある必須脂肪酸です。
DHAは脳神経に有効な成分で、EPAは中性脂肪に有効な成分です。
生活習慣病予防には欠かせません!
ビタミンA・ビタミンB1・ビタミンB2
ビタミンA、ビタミンB1は身より皮のほうが多いんです。ビタミンB2は黒い皮の部分に豊富に入っています。
ビタミンAは、皮膚や粘膜の保護、夜盲症の予防効果などがあります。
脂溶性なので、油と一緒に摂ることで吸収されやすくなりますよ。
オリーブオイルやマヨネーズを使った料理がオススメ。
ビタミンB1は水溶性で水に溶けやすく、熱に弱いので調理する時は長ネギ、玉ねぎ、にんにく、ニラを使った料理がオススメです。
長ネギ、玉ねぎ、にんにく、ニラに含まれるアリシンという成分とビタミンB1が結びつくと熱に強くなり、吸収率もよくなります。
ビタミンB1は糖質をエネルギーに変えるために必要なビタミン。
欠かせない栄養素ですから、しっかり摂りたいですね。
ビタミンB2はビタミンB1と同じく水溶性です。ビタミンB1は熱に弱いんですが、ビタミンB2は熱に強いんですよ。
でも弱点として、光を浴びると減少していってしまいます。蛍光灯の光や太陽光になるべく当てないのがいいんですが、スーパーではガンガン蛍光灯に当たってますから、食べる頃にはビタミンB2は多少減ってしまってます。
ですが、0にはならないので食べないよりはマシです!
ビタミンB2は糖質、タンパク質、脂質の代謝に必要なビタミンで、疲労回復に役立ってくれます。
コラーゲン
鮭の皮で注目する栄養成分は『コラーゲン』
皮と身の間のぬめりの部分にはコラーゲンが含まれてるんですよ(^^)
魚のコラーゲンは豚コラーゲンと比べて7倍も吸収率が高いんです。
鮭に含まれるコラーゲンの量は、日常的に食べられる魚の中でトップクラス!
そのコラーゲンはビタミCと相性がいいので、レモン汁をかけたり、デザートに果物を食べると効率的です。
注意点は焼き過ぎはダメです。パリパリが食感的においしいのはわかりますが、せっかくのコラーゲンが台無し。
焦がさないように程よく火を通しましょう。ムニエルとかアルミホイル焼き、または蒸す料理がいいですよ。
さて、これだけ栄養豊富な鮭の皮ですが、『有害物質がある』、『体に悪い』という噂も聞きます。いったいどうゆうことなのか、みていきましょう。
鮭の皮には有害物質があるの?
一般的に鮭の皮が有害であるといわれている理由は『過酸化脂質』。
オメガ3脂肪酸は熱に弱い性質で、加熱により脂質が酸化して劣化してしまいます。
そうなると、過酸化脂質は体内でジワジワと細胞を酸化させて、動脈硬化やシミなどの原因となります。
なので、鮭を加熱すると脂質が過酸化脂質に変化してしまうから『有害』といわれています。
でも、ガッカリすることはありません。
抗酸化作用のある食べ物を食べればOKです!
野菜やナッツ類も食事の時に食べることで、抗酸化力の強いビタミンCやビタミンEで体の酸化を防げます。
しかも鮭にはアスタキサンチンという最強の抗酸化成分があります!でもちょっと難点が・・・
詳しくはこちらの記事で。
【関連記事】
鮭のアスタキサンチン効果効能は優秀!でも実感しにくい理由とは?
先ほど、オメガ3脂肪酸は熱に弱いとお話しましたが、DHA・EPAは調理の仕方で含有量が変わってくるので、チェックして料理に活かしましょう!
オメガ3脂肪酸(DHA・EPA)は調理方法によって含有量が違う!
2015年にフライ・グリル・フライパン、この3つの調理法でサンマに含まれるDHA・EPAの含有量を調査した結果が発表されています。
【DHA含有量】
- フライ(揚げもの):48%
- グリル:75%
- フライパン:99%
【EPA含有量】
- フライ(揚げもの):43%
- グリル:77%
- フライパン:91%
こうしてみると、揚げた場合が一番損失が大きいですね。
どうして損失が大きかというと、DHA・EPAは約200℃になると分解してしまいます。
揚げる時の油は高温ですよね。だから油にサンマを投入した直後に身が200℃になり、皮近くに多く含まれるDHA・EPAが分解して減ってしまうということなんです。
グリルの場合は、焼いてる時に脂が飛び散ってしまうので、それで減少してしまいます。
フライパンで焼くと脂を逃さず、高温になりすぎないからDHA・EPAを壊さず調理できます。
ぜひ料理する時はフライパンで(^^)
または、上記の研究には含まれていなかった『蒸す』方法もアリですよね。
【参考元】
魚干物の天日乾燥,加熱による過酸化と変異活性の変化(PDF)
サンマのEPA・DHA保持率に及ぼす加熱調理の影響
まとめ
鮭の皮や皮と身の間には私達の体にとって必要な栄養素が入っています。
吸収されやすいコラーゲンも入ってるので、積極的に食べていきたいですね。
ただ、焼き過ぎや食べ過ぎは返って体に毒ですから、加熱しすぎない。1日1切れ程度にしておく。とすれば良いでしょう。
食事はバランスが大切です。それぞれの欠点や毒を打ち消すことで健康が保たれています。
『有害っていわれてるから食べない』ではなく、他の食材と合わせて食べることで有害なものを阻止してくれますから、なるべく好き嫌いせずに色々な食材を食べるようにしましょう(^^)
【関連記事1】
鮭の中骨缶詰の栄養はCa!吸収率を上げる栄養素もご紹介!
【関連記事2】
鮭のアスタキサンチン効果効能は優秀!でも実感しにくい理由とは?